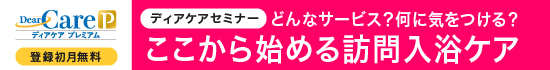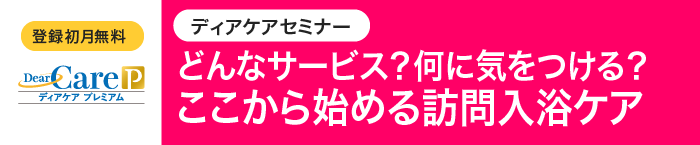- 実践ケア全般・その他 >
- 精神科訪問看護 コモレビナースのオンライン相談室 >
- 第4回 病識を持たない利用者さんとのかかわり方
第4回 病識を持たない利用者さんとのかかわり方
2025年8月公開
この連載では、東京都の精神科訪問看護「コモレビ・ナーシングステーション」のスタッフが、読者のみなさんから寄せられた声をもとに、精神科の利用者さんへのケアのヒントをお届けしていきます。
今回も前回に続き、「精神障害・精神疾患をお持ちの患者様・ご家族様とのかかわりについて」というアンケート(2025年2月実施)にて、ディアケア会員のみなさんから「知りたい」という声が多かったテーマを取り上げます。
今回のテーマは「精神疾患の症状があるが、病識を持っていない利用者さんとのかかわり」。
3名のコモレビスタッフが集い、座談会形式でこのテーマについて考えてみました。
私たち精神科に特化した訪問看護のスタッフが、日々どのように考え、実践しているのか。それを少しでも感じていただけたら嬉しいです。
「病識がない方」のケアにおける「悩み」にはどんなものがありますか?
森本:今日のテーマは「病識を持っていない利用者さんとのかかわり」です。そもそも、利用者さんが「病識を持っていない」とき、看護師としてどのような悩みがあるでしょうか?そこから、今日の対話をスタートしてみたいと思います。
西田:身体科の場合は、患者さんが自分の病名を知っている状態であることが多いと思いますが、利用者さんが自分の病名を知らなかったり、ご本人が違う病名を告げられていることがあったりするというのは、精神科特有の状況かもしれませんね。
病名という共通言語が持てないことで、相手の方と話がかみ合わなかったり、訪問の時間で何をするのかが曖昧になってしまったりするのではないか、というお悩みはありそうだなと思います。
森本:そもそも相手が病識を持っているかどうかが分からない、という状況も珍しくありませんよね。そうしたときにどう病気の話をするかに悩む、という方もいるかもしれないと思います。
佐藤:病識が無い方の場合、医療者が提供する1つ1つの治療の意味を理解できず、例えば服薬ができなかったりする、といったことはあると思います。
また、ご家族へのケアに悩むような局面もあるのかと思います。以前アルコール依存症の方で、飲んで何度も周りに迷惑をかけてしまっている状況という方がいました。ご本人は「困っていない」とのことでしたが、必死でカバーしていたご家族が心身とも限界で入院してしまった、ということがありました。
「ディアケア」に
会員登録(無料)すると
できること
限定コンテンツ
実践のコツや記事などの
「限定コンテンツ」が見られる!
資料ダウンロード(PDF)
一部の記事で勉強会や
説明など便利に使える資料を公開中!
ケア情報メール
新たなコンテンツの
公開情報や、ケアに役立つ情報をお届け!
【有料サービス】「ディアケア プレミアム」に
登録するとできること(月額800円~/無料お試しあり/法人利用も可能)
実践ケア動画
エキスパートのワザやコツが
学べる動画を多数掲載!
期間限定セミナー動画
各分野のエキスパートが登壇。
1回約15分で学べる!
電子書籍
書店で販売されている本や、
オリジナル書籍が読み放題!