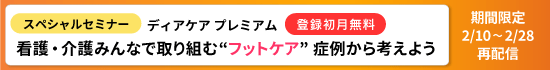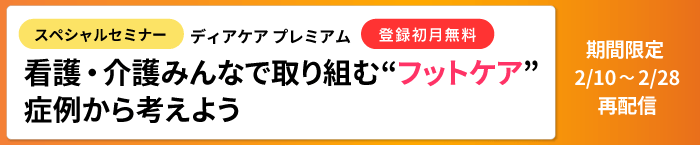- 創傷ケア >
- 糖尿病の「足」を救う 糖尿病足病変と救肢のためのアプローチ >
- (5)「足を救う」ための国をあげての取り組み
- 創傷ケア >
~ 特集 ~
糖尿病の「足」を救う糖尿病足病変と救肢のためのアプローチ
【この記事に関連するより新しいコンテンツがあります(2019年5月公開)】
2017年3月公開
(5)「足を救う」ための国をあげての取り組み
糖尿病足潰瘍によって大切断を余儀なくされる患者をどうするかは、喫緊の課題です。そこで、平成28年度診療報酬改定では「下肢末梢動脈疾患指導管理加算」が新規保険収載となりました(表1)。これは、すべての人工透析患者の足を透析クリニックが日頃からチェックし、重症度の高い虚血がみられる人をスクリーニングして下肢救済を行う専門病院へ紹介すると算定できるというものです。
表1 平成28年度診療報酬改定で新設された下肢末梢動脈疾患指導管理加算
下肢末梢動脈疾患指導管理加算
100点(毎月1回)
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、人工腎臓を実施している患者に係る下肢末梢動脈疾患の重症度等を評価し、療養上必要な指導管理を行った場合には、下肢末梢動脈疾患指導管理加算として、月1回を限度として所定点数に100点を加算する。
下肢末梢動脈疾患指導管理加算は、当該保険医療機関において慢性維持透析を実施しているすべての患者に対しリスク評価等を行った場合に算定できる。その際「血液透析患者における心血管合併症の評価と治療に関するガイドライン」等に基づき、下肢動脈の触診や下垂試験・挙上試験等を実施した上で、下肢末梢動脈の虚血病変が疑われる場合には足関節上腕血圧比(ABI)検査又は皮膚組織灌流圧(SPP)検査によるリスク評価を行っていること。また、ABI検査0.7以下又はSPP検査40mmHg以下の患者については、専門的な治療体制を有している保険医療機関へ紹介を行うこと。当該保険医療機関が専門的な治療体制を有している保険医療機関の要件を満たしている場合は、当該保険医療機関内の専門家と連携を行っていること。
上記の「下肢救済を行う病院」とは、具体的には「血行再建術と創傷治療が同時にできる施設」が望ましいですが、2つの治療を同一の施設でできるところはあまり多くありません。そのため、2つの病院が“病病連携”を行って足の治療を行っていくことになります。そういう意味では、今回の加算は、連携のための加算と言えるでしょう。
下肢末梢動脈疾患指導管理加算については、糖尿病患者さんと医療従事者のための情報サイト「糖尿病ネットワーク」でわかりやすく解説されています(http://www.dm-net.co.jp/footcare/medical-fee/)。このサイトでは、「足病変とフットケアの情報ファイル」というサイトで、足病変の進行に応じたケア、知識、治療をはじめ、さまざまな垣根を越えた知見・実際的な情報を患者と医療従事者に提供しています。その中で、まさに糖尿病の足を救うことを目的として活動している一般社団法人 Act Against Amputationの代表理事である大浦紀彦先生(杏林大学形成外科教授)は、啓蒙のための基礎知識から実践知識までを解説しています(http://www.dm-net.co.jp/footcare/aaa/)。糖尿病足病変にかかわる医療従事者、その中でも重要な看護師の役割を表1のように示し、以下のようなメッセージを発信しています。
「このような処置や教育指導を実践的に行うには、看護師の力が欠かせません。創傷処置を行っている施設から積極的に学び、褥瘡・下肢創傷の処置を看護師が中心となって行っていく体制を院内で構築する必要があります。知識と技術を得るには、日本下肢救済・足病学会の認定師講習などを受講されることをお勧めします。血流評価、スクリーニング、フットケア、創傷処置を看護師のシゴトとしてマスターしてもらい、ぜひ先頭に立って透析患者の足を救っていただけたらと期待しています。」
表1 看護師が行うべきこと
- 1透析クリニックの全患者のフットケアシートを作成し、透析全患者の足を観察し、リスク分類する
- 2ハイリスクの患者の足の状態を1~2週間に一度観察する
- 3ハイリスクでない患者も1か月に一度は、観察しフットケアシートをつける
- 4患者教育を行う
参考文献・サイト
- 1大浦紀彦:下肢救済のための創傷治療とケア.照林社,東京,2011.
- 2大浦武彦,秋野公造:糖尿病・透析の人に役立つ「足病」の教科書.三五館,東京,2016.
- 3上村哲司:高齢化社会の足病変に対する実際の診療−足の褥瘡を治療,予防するためにはどうすればよいのか!.臨床と研究,2015;92(10):109-113.
- 4寺部雄太:糖尿病足潰瘍の治療の実際:創傷治療と免荷~本邦でのOffloadingのススメ.ALmedia,2016;20(5):7-14.
- 5糖尿病ネットワーク.http://www.dm-net.co.jp/(2017.2.27アクセス)
- 6Act Against Amputation—なくそう下肢切断.http://www.dm-net.co.jp/footcare/aaa/(2017.2.27アクセス)