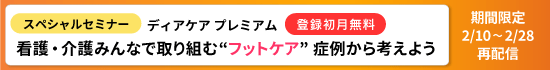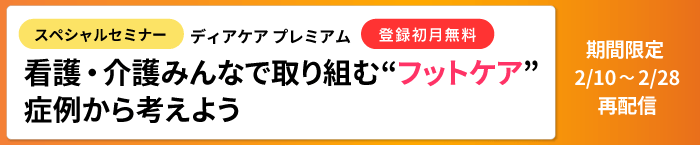- 実践ケア全般・その他 >
- 在宅ケアにICT(情報通信技術)を取り入れるテレナーシング(遠隔看護)の必要性 >
- COVID-19感染拡大で急速に進みつつある「遠隔医療」「遠隔看護」
~ 特集 ~
在宅ケアにICT(情報通信技術)を取り入れる
テレナーシング(遠隔看護)の必要性
2021年11月公開
COVID-19感染拡大で急速に進みつつある「遠隔医療」「遠隔看護」
『エキスパートナース』編集部
- COVID-19感染拡大で急速に進みつつある「遠隔医療」「遠隔看護」
- “テレナーシング”とはどういうもの?
- テレナーシングにはどんなタイプがある?
- テレナーシングを行うための情報通信技術とセキュリティ対策
- テレナーシングを利用した事例から
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大が続く中で、医療機関は逼迫度を増し、自宅で療養せざるを得ない感染者が急増しました。そのため、国では新型コロナウイルス感染症におけるオンライン診療の積極的な展開を推進しつつあります。オンライン診療とは、医師と患者をインターネットでつなぎ、会議システムを使ってオンライン面談をして診療を進めるというものです。
去る2020年4月、厚生労働省では47都道府県などに「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」を通知しました(https://www.mhlw.go.jp/content/000621247.pdf)。主な内容は以下のようなものです。
- ①コロナ禍において、オンライン診療や電話診療、オンライン服薬指導や電話服薬指導は、院内感染の防止に寄与する。
- ②初診からオンライン診療をできるようにする。
- ③医師は処方せんを、患者が希望する薬局に送信することができる。
- ④処方せんを受信した薬局の薬剤師は、患者にオンラインで服薬指導をすることができる。
- ⑤薬局は、処方せんどおりに調剤した薬剤を患者宅に発送することができる。
- ⑥対象疾患を限定しない。
これまでオンライン診療にはいくつか制限がありました。今回の特例ではその制限が大幅に緩められ、特に「初診からオンライン診療可能」と「対象疾患を限定しない」の2つの新ルールが出されたことは画期的と言えるでしょう。
さらに、同省では以下のサイトで、新型コロナウイルス感染症の治療としてオンライン診療を行っている全国の医療機関を紹介しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00014.html
このように、コロナ禍を受けて遠隔医療(Telemedicine)の実践は急速に加速し、同時に遠隔医療の一部である「遠隔看護(Telenursing:テレナーシング)」の必要性も高まってきています。テレナーシングは、インターネットの普及により、近年急速に広がっている新たな看護の提供方法で、遠隔地の看護職(テレナース)がテレビ電話やインターネットなどの情報通信技術を用いて、慢性疾患で在宅療養する方へ看護を行う方法です。さまざまな理由で通院困難な方にも、テレナースが、在宅患者の心身状態を判断して、タイムリーな看護と保健相談を提供できます。
診療報酬上では、2018年に在宅酸素療法指導管理料に遠隔モニタリング加算が新設されました。慢性閉塞性肺疾患(COPD)IIIIV期で在宅酸素療法を受けている利用者に対し、呼吸器科経験のある医師または看護師がICTを活用して、脈拍、酸素飽和度、機器の使用時間や酸素流量などのモニタリングを行うなど、要件を満たせば診療報酬に算定可能となっています。
こうした動きを受け、一般社団法人日本在宅ケア学会ではテレナーシングを実践する場合の一つの指針として『テレナーシングガイドライン』をまとめました。当ガイドラインを編集した一般社団法人日本在宅ケア学会の理事長である聖路加国際大学大学院看護学研究科の亀井智子教授は、「近代看護学はこれまでに多くの患者の健康回復を支援してきました。病院など臨床現場での“第1の看護”、療養者宅を訪問する“第2の看護”、そして今、その延長線上にある“第3の看護”である遠隔看護の必要性が高まってきていると思われます。“病院や臨床”と“訪問”、それに“遠隔”を組み合わせることによって、それぞれの場で生活する人のニーズに合った切れ目のない看護が可能になるのです」と話しておられます。『テレナーシングガイドライン』を元に、テレナーシングの概要をまとめました。
当ガイドラインは下記サイトから閲覧できます。
http://jahhc.com/wp-content/themes/jahhc/pdf/guideline20210817.pdf
書籍『テレナーシングガイドライン』
発行:照林社 https://www.shorinsha.co.jp/books/index.html