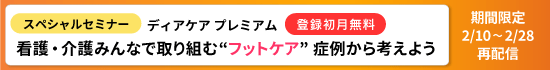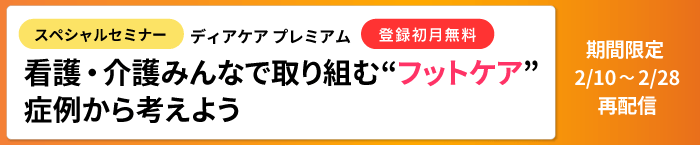- ホーム >
- 実践ケア全般・その他 >
- ALSとは?筋萎縮性側索硬化症の症状と在宅療養生活を支える看護ケア >
- ALS(筋萎縮性側索硬化症)は、どんな疾患?
- ホーム >
- 実践ケア全般・その他 >
~ 特集 ~
ALSとは?筋萎縮性側索硬化症の症状と在宅療養生活を支える看護ケア
2025年1月公開
-
- ALS(筋萎縮性側索硬化症)は、どんな疾患 ?
- ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の進行過程の特徴は ?
- ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の看護とは?
- ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の暮らしを支えるケアとは ?
- ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の在宅療養支援体制とは?
- まとめ:訪問看護師に向けてのメッセージ
ALS(筋萎縮性側索硬化症)は、どんな疾患?
1.ALS(筋萎縮性側索硬化症)とは
筋萎縮性側索硬化症(amyotrophic lateral sclerosis:ALS)は原因不明、かつ根治的治療法が未解明の運動ニューロン疾患で、難病中の難病と呼ばれています。
運動ニューロンが選択的に侵されることで筋肉が萎縮し、運動機能障害、嚥下障害、構音障害、呼吸障害などが次々と引き起こされます。呼吸障害に対しては、人工呼吸器を装着しなければ3~5年で亡くなりますが、人工呼吸器を装着すれば長期間生きることができます。
ALSは孤発型がほとんどですが、遺伝型(約10%)もあります。また発症様式は、表1の4つがあります。
表1 ALSの発症様式
|
なかでも球麻痺型は、病状の進行が特に速いです。しかし、診断初期では四肢の運動障害があまりなく、自分で自分のことができる状態であるため、病識が伴わず、意思決定支援が困難です。
ALSは、人口10万に対して1~3人が発症するまれな病気です。日本のALSの患者数(特定医療費(指定難病)受給者証所持者数)は、ここ数年1万人弱です。男女比は1.3:1と男性がやや多く、年齢は75歳以上が最も多いですが、20代・30代の患者もいます。
2.ALSの最新トピックス
(1)ALSのエビデンスがくつがえる!
ALSにはあらわれにくいとされる症状があり、「褥瘡」「眼球運動障害」「膀胱直腸障害」「感覚障害」の4大陰性徴候が広く知られています。ところが、褥瘡や眼球運動障害のあるALS患者は少なくありません。
またALSは全身が動かなくなるものの、意識や五感は最後まで保たれるといわれてきましたが、ALS患者の約2割に、認知症を伴うALS患者(ALS with dementia:ALS-D)がおり、前頭側頭型認知症(frontotemporal dementia:FTD)との関連が指摘されています。長期人工呼吸療法により、滲出性中耳炎(otitis media with effusion:OME)となり、聴覚に障害をきたす患者もいます。
(2)世界レベルで進む治療薬開発!
現在、ALSには、病状進行を遅らせる薬として、リルゾール(商品名:リルテック)、エダラボン(商品名:ラジカット)があります。前者は内服薬で、後者はこれまで点滴による投与でしたが、2023年4月より経口剤(内用懸濁液)が発売され、患者と医療者の負担が軽減された投与方法になりました。その他、メコバラミン(商品名:ロゼバラミン筋注)が2024年9月に国内製造販売承認を得て、2024年11月頃には、患者投与が開始される予定です。国内外でALSに関する臨床治験が多く進められています。
(3)非運動症状にも着目!
運動機能障害ばかりに目がいきがちですが、非運動症状(痛み、身の置き所のなさ、流涎、情動制止困難など)に対するケアや合併症も着目されています。
ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の進行過程の特徴は?
「ディアケア」に
会員登録(無料)すると
できること
限定コンテンツ
実践のコツや記事などの
「限定コンテンツ」が見られる!
資料ダウンロード(PDF)
一部の記事で勉強会や
説明など便利に使える資料を公開中!
ケア情報メール
新たなコンテンツの
公開情報や、ケアに役立つ情報をお届け!
【有料サービス】「ディアケア プレミアム」に
登録するとできること(月額800円~/無料お試しあり/法人利用も可能)
実践ケア動画
エキスパートのワザやコツが
学べる動画を多数掲載!
期間限定セミナー動画
各分野のエキスパートが登壇。
1回約15分で学べる!
電子書籍
書店で販売されている本や、
オリジナル書籍が読み放題!