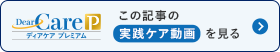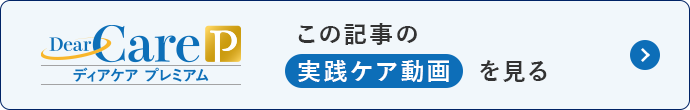- 排泄ケア >
- 新たな段階に移る“便秘ケア” >
- (1)便秘の定義・分類が変わった
- 排泄ケア >
~ 特集 ~
新たな段階に移る“便秘ケア”
※この記事は、公開年月現在の情報です。ご留意の上お読みください。
2019年4月公開
(1)便秘の定義・分類が変わった
畠山 誠
医療法人札幌ハートセンター
札幌心臓血管クリニック、皮膚・排泄ケア認定看護師
2017年に『慢性便秘症診療ガイドライン』が出版されました。編集は、日本消化器病学会の関連研究会である「慢性便秘の診断・治療研究会」です。当ガイドラインは、原案が作成された後、外部評価委員の評価を経て、日本消化管学会、日本大腸肛門病学会、日本神経消化器病学会から寄せられたパブリックコメントをもとに修正されて出版されたものです。
ガイドラインでは、“便秘”の定義を、「本来体外に排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態」としています1。つまり、便秘は“疾患名”でも“症状名”でもなく、“状態名”であると規定しているのです。その状態とは、「排便回数や排便量が少ないために糞便が大腸内に滞った状態」、あるいは「直腸内にある糞便を快適に排出できない状態」です。
これまで、便秘は、「器質性」「症候性」「薬剤性」「機能性」に分類されていました。今回のガイドラインでは、まず、便秘の原因として、「器質性」と「機能性」に分類します。「器質性」は「狭窄性」と「非狭窄性」に分けられます。そして、「非狭窄性」と「機能性」は、それぞれ「排便回数減少型」と「排便困難型」に分けられるという構造です。この「排便回数減少」と「排便困難」というのが、「症状」になります。看護師は、患者さんの訴えや症状に接することが多いですが、「排便回数減少」のめやすは「週3回未満の排便」、「排便困難」とは「直腸内の糞便の排出が十分でなく残便感がある」状態です。
さらに、「病態」として、「大腸通過正常型」「大腸通過遅延型」「便排出障害」に分けられます(表1)。「大腸通過正常型」は、排便回数や排便量が少なく、主な原因は食物繊維摂取不足です。そのため、適正に食物繊維をとること(目標は1日に18~20g)で改善することが多く、生活指導が重要になります。「大腸通過遅延型」「便排出障害」では、食物繊維の摂取量を増やしても改善しないことが多いため、適切な下剤等の投与が必要になります。こうしたことを前提にして、正しい病態の変化に応じた“便秘ケア”について考えていきましょう。
表1 慢性便秘(症)の分類
横にスクロールしてご覧いただけます。
| 原因分類 | 症状分類 | 分類・診断のための検査方法 | 専門的検査による病態分類 | 原因となる病態・疾患 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 器質性 | 狭窄性 | 大腸内視鏡検査、注腸X線検査など | 大腸癌・クローン病、虚血性大腸炎など | ||
| 非狭窄性 | 排便回数減少型 | 腹部X線検査、注腸X線検査など | 巨大結腸など | ||
| 排便困難型 | 排便造影検査など | 器質性便排出障害 | 直腸瘤、直腸重積、巨大直腸、小腸瘤、S状結腸瘤など | ||
| 機能性 | 排便回数減少型 | 大腸通過時間検査など | 大腸通過遅延型 | 特発性 症候性:代謝・内分泌疾患、神経・筋疾患、膠原病、便秘型過敏性腸症候群など 薬剤性:向精神薬、抗コリン薬、オピオイド系薬など |
|
| 大腸通過正常型 | 経口摂取不足(食物繊維摂取不足を含む) 大腸通過時間検査での偽陰性など |
||||
| 排便困難型 | 排便造影検査など | 硬便による排便困難 | 硬便による排便困難・残便感(便秘型過敏性腸症候群など) | ||
| 機能性便排出障害 | 骨盤底筋協調運動障害 腹圧(怒責力)低下 直腸感覚低下 直腸収縮力低下 など |
||||
「日本消化器病学会関連研究会慢性便秘の診断・治療研究会編:慢性便秘症診療ガイドライン2017,p.3,2017,南江堂」より許諾を得て改変し転載
引用文献
1.日本消化器病学会関連研究会 慢性便秘の診断・治療研究会 編:便秘の定義.慢性便秘症診療ガイドライン2017.南江堂,東京,2017:2.
- (1) 便秘の定義・分類が変わった
- (2) 下剤使用はルーチンで行わないことが大事
- (3) 便排出障害の患者に大腸刺激性下剤を使用していないか
- (4) 大腸刺激性下剤の長期連用に注意
- (5) 少量の下痢の持続に注意
- (6) 退院後に必要なケアを見通した排便ケアを