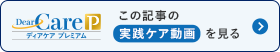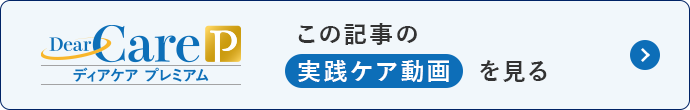- 運動器ケア >
- 転倒リスクに気づき、転倒を予防する >
- 患者さんが転倒せずに日常生活を送るために
- 運動器ケア >
~ 特集 ~
転倒リスクに気づき、転倒を予防する
2019年11月公開
患者さんが転倒せずに日常生活を送るために
編集 上内哲男
独立行政法人 地域医療機能推進機構(JCHO)東京蒲田医療センター
リハビリテーション科 リハビリテーション士長
日本転倒予防学会理事
専門理学療法士(生活環境支援/運動器)
転倒予防の目的は、“転倒しない”ことではありません。転倒せずに日常生活ができるように支援することが重要なのです。
患者さんを転倒させまいと安易な抑制を行うと、身体機能を低下させ、生活の質を落とします。必要なのは、患者さんが安全に行動できるための環境とケアを考えることです。
病院での転倒が起こった際、転倒した患者さんの1.85%が、重大な怪我(重度、死亡、手術、ギプスが必要な骨折、神経損傷など)につながったと報告されています1。転倒による脳外傷や大腿骨骨折などの重大事故を防ぐことが大切です。
そのためにも、患者さんの一番身近な存在である看護師が、転倒のリスクをしっかりと認識し、患者さんにかかわる必要があります。
なお、日本医療安全調査機構による「入院中に発生した転倒・転落による頭部外傷に係る死亡事例の分析」2のなかで、「転倒・転落予防対策の取り組みは、患者の日常生活を担っている看護師を中心に行われていることが少なくない。一方で、高齢化社会が進む我が国において、複雑なリスクをもつ高齢者や認知症・せん妄患者は今後も増加が予測されており、看護師だけで転倒・転落予防に取り組むことには限界がある」と述べられています。
自分1人だけで転倒予防に取り組むのではなく、多職種で転倒リスクを評価・精査し、患者さんが転倒せずに安全に日常生活を送るための対策を考え、実践していきましょう。そして、その対策の効果を検証し、フィードバックしていくことも大切です。
このように、多職種が連携して転倒予防に取り組むことで、転倒事故の低減に寄与するものと信じています。
- 一般社団法人日本病院会 QIプロジェクト:平成29年度医療の質の評価・公表等推進事業結果報告.
https://www.hospital.or.jp/qip/past.html(2019年9月20日アクセス) - 一般社団法人日本医療安全調査機構(医療事故調査・支援センター):医療事故の再発防止に向けた提言 第9号 入院中に発生した転倒・転落による頭部外傷に係る死亡事例の分析(2019年6月).
https://www.medsafe.or.jp/uploads/uploads/files/teigen-09.pdf(2019年9月20日アクセス)
無料会員登録で全文読み放題!