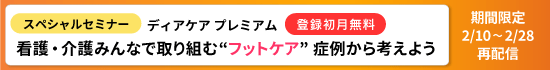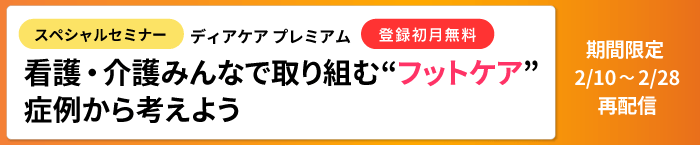- 運動器ケア >
- 転倒に関するステートメントと介護予防 >
- 転倒に関する4つのステートメント
- 運動器ケア >
~ 特集 ~
転倒に関するステートメントと介護予防
2021年9月公開
- 転倒に関する4つのステートメント
- 寝たきりにもつながる高齢者の転倒による骨折
- 高齢者の転倒はさまざまな要素が相互に影響して発生する
- 運動機能を向上させる“介護予防”の具体策
転倒に関する4つのステートメント
『エキスパートナース』編集部
「介護施設内での転倒に関するステートメント」は、日本老年医学会の「老年症候群の観点から見た転倒予防とその限界に関する検討ワーキンググループ」における2年間の検討を踏まえてまとめられたものです。
声明の意図するところは、転倒やそれに伴う傷害に関して、防止しようとする施設の姿勢や取り組みと、発生した事故を状況に応じて受容する入所者、家族、ひいては国民全体の心象とのバランスのありようを、把握しうる範囲で科学的に検討したものである、とされています。
ステートメントは以下の4項目です。
ステートメント1:転倒すべてが過失による事故ではない
転倒リスクが高い入所者については、転倒予防策を実施していても、一定の確率で転倒が発生する。転倒の結果として骨折や外傷が生じたとしても、必ずしも医療・介護現場の過失による事故と位置付けられない。
ステートメント1は、一般の人に広く知ってほしい項目と言えます。施設で転倒が起こった場合、まず「事故」として処理され、施設の管理者や職員(看護職・介護職)が、その責を問われることが多いでしょう。そのため、この認識の共有は、転倒発生後ではなく入所時などに事前に行われておく必要があります。
ただし、施設内での転倒は必ずしも“過失”とは言えませんが、どのような状況下で転倒が発生したのかを施設内で検証し、その後の転倒予防に活かすための体制づくりが求められると解説されています。
ステートメント2:ケアやリハビリテーションは原則として継続する
入所者の生活機能を維持・改善するためのケアやリハビリテーションは、それに伴って活動性が高まることで転倒リスクを高める可能性もある。しかし、多くの場合は生活機能維持・改善によって生活の質の維持・向上が期待されることから原則として継続する必要がある。
介護施設で日常的に行われているリハビリテーションは、身体機能の維持・向上だけでなく精神的サポートの意味合いでも奨励されるものですが、一方で、一定の確率で転倒リスクが生じます。転倒リスクだけに目を向けるのではなく、さまざまな要素を総合的に判断することが必要になります。
ステートメント3:転倒についてあらかじめ入所者・家族の理解を得る
転倒は老年症候群の1つであるということを、あらかじめ施設の職員と入所者やその家族などの関係者の間で共有することが望ましい。
老年症候群というのは、高齢者に多く認められる転倒、尿失禁、褥瘡、せん妄などの多彩な症候の総称です。転倒はあくまでも老年症候群の1つであり、転倒リスクが高い人では転倒に基づく骨折や死亡は老年症候群の自然経過として一般的であることを強調しています。そして、施設では原則として身体拘束を行わないことになっていますが、高齢になればなるほど転倒予防対策の効果がきわめて限定的であると述べています。
ステートメント4:転倒予防策と発生時対策を講じ、その定期的な見直しを図る
施設は、転倒予防策に加えて転倒発生時の適切な対応手順を整備し職員に周知するとともに、入所者やその家族などの関係者にあらかじめ説明するべきである。また、現段階で介護施設において推奨される対策として標準的なものはないが、科学的エビデンスや技術は進歩を続けており、施設における対策や手順を定期的に見直し、転倒防止に努める必要がある。
今回のステートメントは介護施設での転倒についてのものですが、病院において転倒防止はより重要な指標の1つと言えます。医療訴訟の盛んな欧米では、転倒事故による訴訟リスクを避けるためにも、転倒防止のためのマニュアル作成や、転倒事故発生時の対応マニュアル等が整備されています。病院ほどではないにしても、介護施設においても各施設の状況に応じた施設独自の対応マニュルを整えておく必要があるでしょう。この提言の中では、一般的な対策項目として、転倒リスクの評価、運動(リハビリテーション)に加え、服用薬の見直しなど修正可能なリスクへの多面的な介入について紹介しています。そして、有用な情報として、日本転倒予防学会による『転倒予防白書』を挙げています。