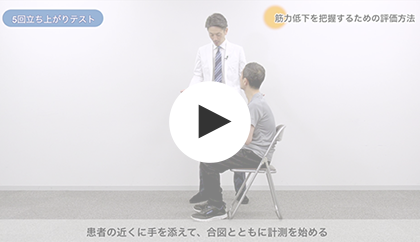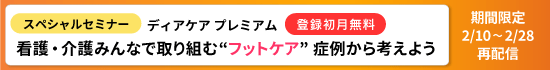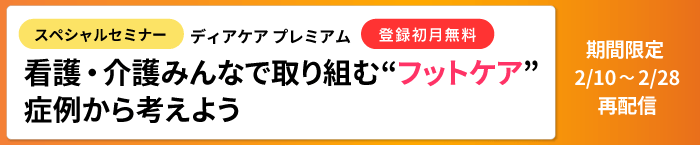- 運動器ケア >
- 転倒に関するステートメントと介護予防 >
- 運動機能を向上させる“介護予防”の具体策
- 運動器ケア >
~ 特集 ~
転倒に関するステートメントと介護予防
2021年9月公開
- 転倒に関する4つのステートメント
- 寝たきりにもつながる高齢者の転倒による骨折
- 高齢者の転倒はさまざまな要素が相互に影響して発生する
- 運動機能を向上させる“介護予防”の具体策
運動機能を向上させる“介護予防”の具体策
『エキスパートナース』編集部
介護予防とは、「高齢者が要介護状態等となることの予防、または要介護状態等の軽減、もしくは悪化の防止を目的として行うもの」とされています。そして、厚生労働省では、以下のように規定しています。
生活機能の低下した高齢者に対しては、リハビリテーションの理念を踏まえて、「心身機能」「活動」「参加」のそれぞれの要素にバランスよく働きかけることが重要であり、単に高齢者の運動機能や栄養状態といった心身機能の改善だけを目指すものではなく、日常生活の活動を高め、家庭や社会への参加を促し、それによって一人ひとりの生きがいや自己実現のための取組を支援して、QOLの向上を目指すものである。
(厚生労働省「これからの介護予防」)
介護予防を具体的に進めるために、国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター老年学・社会科学研究センターでは、「介護予防ガイド―実践・エビデンス編」を公開しました。これは平成31年度-令和2年度厚生労働省科学研究費(長寿科学政策研究費事業)「エビデンスを踏まえた効果的な介護予防の実施に資する介護予防マニュアルの改訂のための研究」(研究代表者・荒井秀典)によるもので、エビデンスに基づいた介護予防事業が実施できるようにまとめたものです。以下のサイトからダウンロードできます。
https://www.ncgg.go.jp/ri/topics/documents/yobo-guide.pdf
章立てとしては、①運動機能向上マニュアル(全般)、②運動器疾患用マニュアル、③呼吸循環器疾患用マニュアル、④糖尿病用マニュアル、⑤脳卒中用マニュアル、⑥栄養改善マニュアル、⑦口腔機能向上マニュアル、⑧閉じこもり予防・支援マニュアル、⑨認知機能低下予防マニュアル、⑩うつ予防・支援マニュアル、に分かれています。
ここでは、転倒防止に関連する「運動機能向上マニュアル(全般)」の内容から運動プログラムの部分を抜粋して紹介します。
運動プログラムの具体的内容
高齢者に対して運動介入を行った先行研究におけるプログラムの中で最も多く採用されているのは「筋力トレーニング」です。また、筋力トレーニング、バランス運動などを複数取り入れたマルチコンポーネント介入が行われており、介護予防においても、筋力トレーニングを含むマルチコンポーネント介入が奨められます。
1. ストレッチング
運動による傷害を予防するために、運動前のウォーミングアップや運動後のクールダウンとしてストレッチングを実施します。ストレッチングのポイントは、ゆっくりと深呼吸をしながら、痛みの生じない範囲で筋肉を伸ばすことです。
2. 筋力トレーニング
筋力トレーニングにより、筋力やバランス能力、歩行速度、持久力などが向上することが示されています。筋力トレーニングには坐位でのトレーニングと立位でのトレーニングがあり、対象者の機能や疼痛の有無に応じて使い分けることとされています。
①坐位で実施可能なトレーニング:運動機能低下やフレイル、サルコペニアを有する高齢者に対しては、まず坐位で可能なトレーニングから始めます。転倒歴があったり、転倒恐怖感を持っていたり、疼痛がある人に対しても坐位トレーニングを行います。
・立ち座り運動(大腿四頭筋、大殿筋の強化)
・膝伸ばし運動(大腿四頭筋の強化)
・脚開き運動(股関節外転筋の強化)
・太もも上げ運動(腸腰筋の強化)
・踵上げ運動(下腿三頭筋の強化)
②立位で実施可能なトレーニング:運動機能が良好な高齢者に対しては立位でのトレーニングを積極的に行います。フレイル、サルコペニアの高齢者でも坐位でのトレーニングに慣れてきたら立位のトレーニングも取り入れます。
・スクワット(大腿四頭筋、大殿筋の強化)
・脚の横上げ(股関節外転筋の強化)
・踵上げ(下腿三頭筋の強化)
・片脚上げ
3. ウォーキング
正しい姿勢で歩くためには、目線を歩く方向に向けて背筋を伸ばし、腕を大きく後に振り、踵から地面に着くようにします。
4. バランス運動
身体が不安定な状況下で姿勢を保つ必要があるため、能力に応じて坐位での運動を選択したり、支持物を使用することで転倒しないように配慮した上で行います。坐位でのバランス運動と立位でのバランス運動があります。
- ※上記の「ストレッチング」「筋力トレーニング」の実際については、わかりやすく動画で紹介している下記サイトをご覧ください。