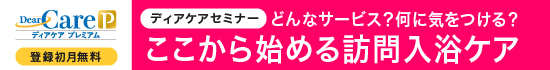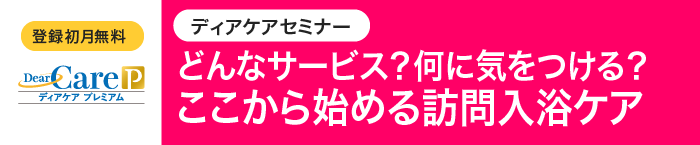- 身体ケア >
- 訪問入浴ケア 在宅での安全・安楽な入浴のために看護職が知っておきたいこと >
- 入浴がもたらす効果
- 身体ケア >
~ 特集 ~
訪問入浴ケア
在宅での安全・安楽な入浴のために看護職が知っておきたいこと
2025年9月公開
入浴がもたらす効果
渡辺 忍
茨城県立医療大学保健医療学部
看護学科 准教授
1.入浴による作用
入浴の安全性や有効性を検討するうえで必要な知識として、入浴の7大作用を押さえておきましょう。
1)温熱作用
入浴に伴う温熱が身体に及ぼす作用です。体温上昇によって生理機能が活発になります。
2)静水圧作用
浴槽のお湯の圧が身体にかかり、血流や生理機能に影響を与える作用です。1mの水深では、1cm2あたり100gの水圧がかかるとされます。例えば、首まで浸かった状態で腹囲を測定すると、空気中に比べて3~5cmほど縮むくらいの圧がかかるといわれています。
3)浮力作用
水の中で物体が上向きに押される作用です。実際に首まで浸かった場合、水の中での体重は約10分の1程度にまで減少します。
4)清浄作用
皮膚や体表粘膜を清浄することにより、身体にとって有害な物質、余分な油脂などを除去し、皮膚や粘膜からの有害物質の体内侵入を予防します。
5)蒸気・香り作用
入浴時に発生する蒸気を吸い込むことにより、口腔内や鼻腔内の粘膜を潤す作用です。また、温泉などの香りは自律神経の調整に効果を発揮します。
6)粘性・抵抗性作用
お湯の中で身体を動かそうとすると、水の抵抗で、陸上の約3~4倍の負荷がかかります。これをうまく利用すると、少ない負担で運動療法的な効果が得られます。
7)解放・密室作用
入浴のため衣服を脱ぐことで、心と体が解放されます。1人の場合は「究極のリラックス空間」となり、公衆浴場などでは他者との「裸のコミュニケーション」空間となるでしょう。
参考文献
- 早坂信哉,古谷暢基:入浴検定 公式テキスト お風呂の「正しい入り方」.日本入浴協会,東京,2017.
訪問入浴ケア