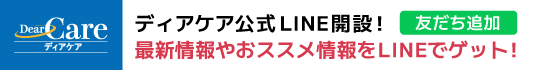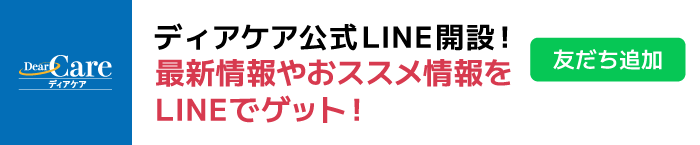- 創傷ケア >
- 医療関連機器圧迫創傷(MDRPU)をどう防ぎ、どうケアするか >
- (1)医療機器によってできる創傷と患者QOLの関係
- 創傷ケア >
~ 特集 ~
医療関連機器圧迫創傷(MDRPU)をどう防ぎ、どうケアするか
MDRPU「医療関連機器圧迫創傷」の名称を「医療関連機器褥瘡」に変更することが2024年2月に日本褥瘡学会用語集検討作業部会から発表がありました。
■関連ニュース(2024年4月)
・医療関連機器“圧迫創傷”から医療関連機器“褥瘡”へ 用語の見直しが進む2017年1月公開
- ※この記事内容は公開当時の情報です。ご留意ください。
(1)医療機器によってできる創傷と患者QOLの関係
医療機器は「ME(medical engineering)機器」とも言われ、医薬品医療機器等法により、次のように定義されています1。
「医療機器とは、人もしくは動物の疾病の診断、治療もしくは予防に使用されること、または人もしくは動物の身体の構造もしくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具などであって、政令で定めるものをいう」
つまり、「診断・治療・予防に使用されること」そして、「身体の構造・機能に影響することを目的としていること」が特徴です。そう考えると、医療現場で使われている機器はすべて医療機器であると言えるでしょう。

これらの機器は有効な使い方によって効果的な治療・ケアを進めることができますが、同時に、効果を追及するあまり生じる弊害も見逃せません。その最たるものが「圧迫による創傷」です。ただ、難しい問題もはらんでいます。特にクリティカルケアの領域では、効果を高めようとするばかりに圧迫が強くなって発生してしまう創傷もあるからです。例えば、酸素マスクは、酸素の有効投与量を維持しようとすればきちんとしたフィッティングが必要になります。酸素の漏れ(リーク)を防ぐために密閉できる強さをもたせると、マスクによる圧迫によって皮膚が傷ついてしまいます。その創傷の予防は、治療による効果よりも優先度が低いのでしょうか。そんなことはありません。「適正なフィッティング方法」によって創傷ができないような適度な強さを維持できれば、患者は創の痛みに苦しむことはありません。それは「患者QOL」にとって非常に大事なことです。
クリティカルケア看護の指導的な立場にある道又元裕先生(杏林大学医学部付属病院看護部長)は、「医療機器によって発生する創傷は、治療においては“合併症”の一つとして取り扱われるべきもので、けっして“仕方ない”ことではなく、予測して防がなければいけないことです」と言います2。
これらの圧迫創傷に対して、これまで現場の看護師は「自らの工夫」によって何とか損傷を少なくしようとしてきました。それぞれの施設で身近にあるものを使って、圧迫・密着・ずれを防ごうとしてきました。道又先生は、「例えば酸素マスクには耳にかけるゴム紐がありますが、これによって耳介部に潰瘍や損傷が引き起こされます。ナースは、メーカーに改良を訴えてきましたが、なかなか実現しませんでした。そのため看護師は、耳と紐との間にガーゼを挟んでみたりゴム紐を包帯に変えてみたり、さまざまな工夫をしましたが、あまり効果はありませんでした。工夫にも限界があるのです」と言います。このような医療機器によってできる創傷・潰瘍に対するスタンダードケアの必要性は、現場のナースならば誰でも感じていました。
引用文献
- 1日本褥瘡学会編:ベストプラクティス医療関連機器圧迫創傷の予防と管理.照林社,東京,2016:6.
- 2道又元裕:クリティカルケア領域では優先度が低いMDRPU,領域を超えた共通の課題として産学共同で取り組みたい.エキスパートナース2016;32(3):52.