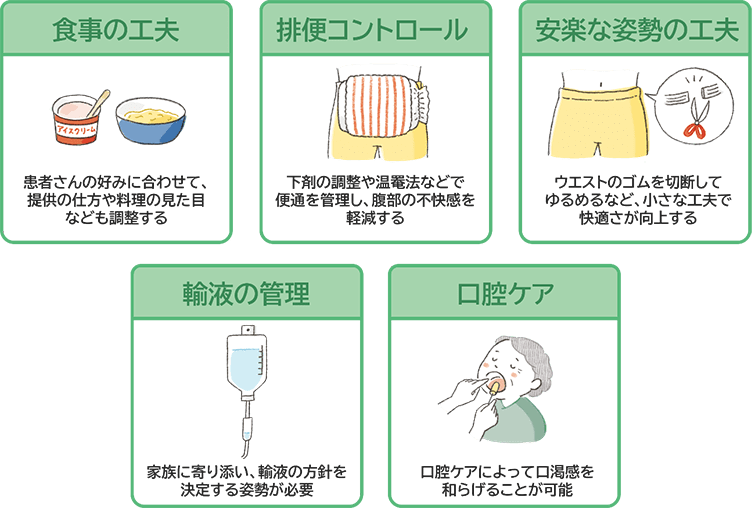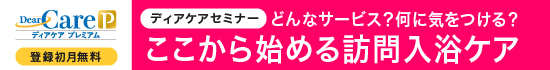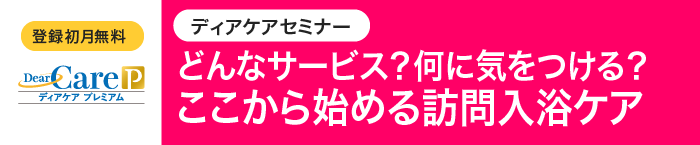- ターミナルケア・看取り >
- どう変化?どう対応?看護職・介護職が知っておきたい 臨終期(看取り期)の症状と経過に合わせたケア >
- 3.臨終期の「食べられない」を支援する
~ 特集 ~
どう変化?どう対応?看護職・介護職が知っておきたい
臨終期(看取り期)の症状と経過に合わせたケア
2025年3月公開
予後が1か月を切るタイミングとは?
3.臨終期の「食べられない」を支援する
細井 崇弘
細井 崇弘
一般社団法人LA会 つくばLAファミリークリニック 院長
(2026年2月開院予定)
一般社団法人LA会
つくばLAファミリークリニック 院長
(2026年2月開院予定)
「食べたいけど食べられない」。食に関する苦悩は、臨終期のケアの現場で避けては通れません。患者さんや家族にとって、臨終期の栄養に関する問題は大きな精神的負担になります。看護職や介護職としてどのようにサポートできるのか、患者さんや家族の「食」に関する苦悩に寄り添うためのケアについて考えてみましょう。
「ディアケア」に
会員登録(無料)すると
できること
限定コンテンツ
実践のコツや記事などの
「限定コンテンツ」が見られる!
資料ダウンロード(PDF)
一部の記事で勉強会や
説明など便利に使える資料を公開中!
ケア情報メール
新たなコンテンツの
公開情報や、ケアに役立つ情報をお届け!
【有料サービス】「ディアケア プレミアム」に
登録するとできること(月額800円~/無料お試しあり/法人利用も可能)
実践ケア動画
エキスパートのワザやコツが
学べる動画を多数掲載!
期間限定セミナー動画
各分野のエキスパートが登壇。
1回約15分で学べる!
電子書籍
書店で販売されている本や、
オリジナル書籍が読み放題!