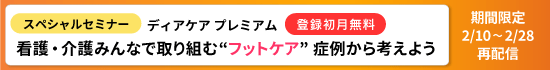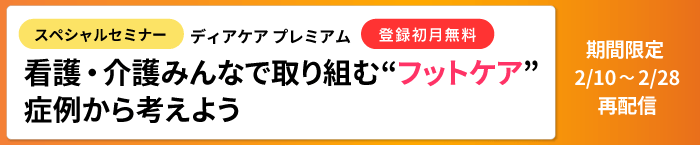ニュース
2016/10/26
相変わらず多い「薬」をめぐるインシデント、アクシデント
公益財団法人日本医療機能評価機構が、7月に公開した医療安全情報〔No.116〕は、「与薬時の患者取り違え」に関する注意喚起であった。また、9月に公開した医療安全情報〔No.118〕では、「外観の類似した薬剤の取り違え」について警鐘を鳴らしている。どちらも、きわめて基本的な医療安全対策の重要性を訴えているものだ。
■与薬時の患者取り違えに関する事例
与薬時、患者氏名の確認が不十分であったため、患者を取り違えた事例は、2013年1月1日~2016年5月31日までの間に6件報告されているという。これらの事例は、異なる氏名を読み上げたにもかかわらず患者が「はい」と答えたり、薬包とネームバンドの患者氏名を照合しなかったりと氏名確認に端を発したケースが多い。
例えば、看護師が患者Bさんの氏名が記載してある薬を持って患者Aさんの元へ行き、薬袋の氏名を見せながら「Bさんですね」と口頭で確認。するとAさんは「はい」と答え、Bさんが飲むはずだったフロセミド錠40mgを1錠内服したというもの。看護師は、その直後にAさんのネームバンドに記載された氏名が違うことを把握し、間違いに気づいている。
他の事例では、看護師が患者Cさんに睡眠薬を投与する際、同性同年代の患者DさんをCさんと思い込み、病室で薬包の患者氏名とネームバンドを照合しないまま胃管から投与したというもの。Dさんが舌根沈下を起こしたときに、看護師がDさんには睡眠薬の指示がなかったことに気づいたという。
他にも、姓だけで確認や、名乗れない患者のネームバンドを確認していなかったなどの事例が報告されている。同機構では、与薬時に薬包などの氏名とネームバンドを必ず照合することや、口頭で患者確認をする際はまず患者に氏名を名乗ってもらった上で薬包などの氏名と照合するなど、きわめて基本的な予防策を紹介している。
■見た目が似た薬剤投与の事例
また、見た目が似た薬を医師や薬剤師らが誤って使ったケースが2010年1月1日~2016年3月31日までに計24件あったという報告書も出されている。これは、全国約1000の医療機関を対象にした医療事故情報の収集事業で報告された事例を分析したもので、患者自身が薬剤を誤って内服したケースは除外している。報告書によると、24件の内訳は注射薬10件、内服薬6件、外用薬5件、その他3件であった。注射薬では薬剤を入れたガラスの容器(アンプル)の形が似ていたのもが7件、内服薬では包装の外観が似ていたのが5件となっている。
取り違えが起きた場面は、注射薬では9件が薬剤の準備中で、主に関わっていたのは助産師・看護師が6件、医師が3件。内服薬6件はすべてが調剤中で、いずれも薬剤師が関わっていたという。24件のうち23件は患者に使われていたが、死亡例はなかったという。ただ、障害が残った可能性がある事例が3件あったということは重大だ。
製薬業界では、アンプルや内服薬の包装、外用薬の容器などにバーコードを表示する取り組みをしている。今後、このバーコードを薬剤の照合に使うことが重要な事故防止対策になると期待される。
詳しくは、下記の日本医療機能評価機構Webサイト参照
http://www.med-safe.jp/
- ※この記事内容は公開当時の情報です。ご留意ください。
×close
ページを印刷したい方へ
×close