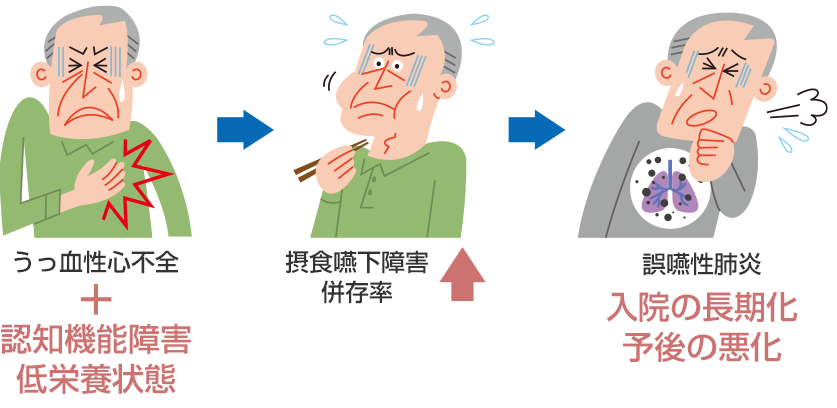2018/1/25
もっと知りたい方はこちら
特集:変わる!認定看護師制度
現場のナースが知りたい最新情報
我が国の認定看護師は18,728人になった(平成29年11月現在)。公益財団法人日本看護協会では、1996年の認定看護師制度開始から20年を経て、さまざまな医療・保健・福祉状況の変化に応じた認定看護師制度の見直しを始めている。現在、認定看護分野21分野、教育課程数100課程、総数18,000人余りに育ち、臨床現場での実践能力は高く評価されている。認定看護師・専門看護師などの看護スペシャリストと診療報酬の関係は見逃せないだろう。認定看護師を配置要件とする診療報酬項目は20項目あり、認定21分野のうち16分野がその対象となっている。認定看護師の分野別の数は、それに呼応しているとも言える。感染管理、皮膚・排泄ケア、緩和ケアなどがまさにそれに該当し、2,000人を超える認定看護師を輩出している。1000人を超える分野は、がん化学療法看護、救急看護、集中ケアなどで、これも診療報酬と深く結びついている。ただ、ここに来て、閉講する教育機関や定員に充足しない課程が増えてきており、医療ニーズとの関連から、求められる看護スペシャリスト像を見直す時期にきているのは確かだろう。
看護スペシャリスト制度の見直しは、社会の変容に応じた医療構造の変化と密接に結びついている。1990年代には医療の高度化・細分化に伴って看護の専門分化が進んできたが、超高齢多死社会を迎えつつある今、病院中心の医療から地域・在宅への移行が急速に進められている。地域包括ケアシステムの構築を見据えた医療の大きな動きの中で、看護師に求められる能力も変化してきていると言えよう。その具体的な現れの一つが「特定行為に係る看護師の研修制度(特定行為研修)」との兼ね合いである。特定行為研修は、看護師が手順書により特定行為を行う場合に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修であり、国ではいっそう特定行為研修を行う指定研修機関の増加を働きかけている。このように特定行為研修への誘導が国をあげて行われている以上、認定看護師制度の再構築が必要なことは言うまでもないだろう。
そこで、日本看護協会が今後の認定看護師教育をどのように考え、その再構築をどう図っていくのかについて紹介しよう。これは、2017年11月18日に開催された平成29年度認定看護師キャリアアップ研修会において荒木暁子・常任理事が、「認定看護師制度のさらなる発展に向けて-認定看護師制度の再構築-」として発表した内容である。
同協会では、特定行為研修制度を活用して認定看護師制度の価値を維持・向上させるという基本方針の下に、これからの認定看護師への期待として、従来のアセスメントに基づく質の高い看護実践に加えて、臨床推論・病態判断などの医学的知識をベースとした能力を養成したいと考えているようだ。つまり、認定看護師教育+特定行為研修という考え方だ。それにより病院だけでなく地域・在宅などのあらゆる場で臨床推論力や病態判断力が向上し、医師をはじめとした他職種との対話力が養えるとしている。そこで、「認定看護師制度再構築により目指す認定看護師の役割(案)」として以下のように示している。
認定看護師制度再構築により目指す認定看護師の役割(案)
認定看護師は特定の看護分野において、以下の3つの役割を果たす
これからの認定看護師に求められる能力としてポイントになるのは「臨床推論力」と「病態判断力」であろう。また、指導・相談において「看護職等」と記述されている点も重要だ。相談・指導の対象は看護職だけでなく、介護職やその他の医療職に対しても行う必要があるということだろう。
具体的にはどのように再構築・移行を図っていくのだろうか。1つ目は、認定看護師教育に特定行為研修を組み込むこと、2つ目は認定看護分野の再編、そして3つ目として現行制度から新たな認定看護師制度への移行をどう進めるか、である。同協会ではそれぞれに関する具体策、あるいはイメージ案を示している。ただ、これらはあくまでも検討中のものであり、今後、行政や関連団体、関係学会との話し合いの中で、具体的な将来像が描かれていくものと思われる。特に2つ目の認定看護分野の再編は、これまで認定看護師が果たしてきたさまざまな役割を見直しながら、社会的なニーズのもとで慎重に検討される必要があるだろう。同協会では、新たな認定看護師教育の開始を2020年からと見越しているという。
詳しくは、下記の日本看護協会Webサイト参照
https://www.nurse.or.jp/nursing/cn/index.html
×close
×close