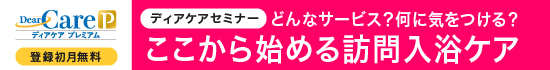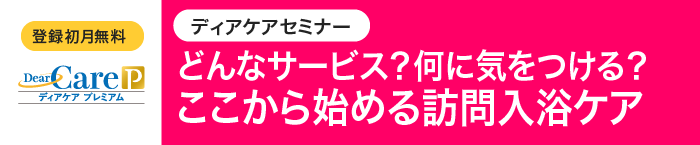ニュース
2019/7/19
入院中に発生した転倒・転落による頭部外傷に係る死亡事例からの提言
転倒・転落はどのような環境にあっても最も起こりやすいインシデント・アクシデントであり、看護師の関心は高い。一般病床における転倒・転落発生率は1日1,000床あたり1.5件程度とされており、加齢とともにその発生率も高くなるといわれる。そのため、院内での転倒・転落予防対策は医療安全上の重要課題の1つである。
日本医療安全調査機構は、「入院中に発生した転倒・転落による頭部外傷に係る死亡事例の分析」を公表した。本分析では、2015年10月~2018年12月に同機構へ報告された事例のうち、11の頭部外傷による死亡事例を扱っている。同センターは、院内における医療事故の再発防止に向けた対応として下記8つの提言をまとめているので紹介する。
■転倒・転落後の診断と対応
提言1:
●転倒・転落による頭部打撲(疑いも含む)の場合は、明らかな異常を認めなくても、頭部CT撮影を推奨する
- 受傷直後に意識レベルなどの神経学的所見に異常がなくても、その後急速に症状が悪化し、死に至る可能性がある。
- 意識レベル、麻痺、瞳孔所見などの神経学的所見やバイタルサインを経時的かつ頻回に観察する。
【ポイント】
本人の訴えや頭部の皮膚所見の有無にかかわらず、急激な血腫増大による頭蓋内圧亢進症状を呈することがある。
提言2:
●抗凝固薬・抗血小板薬内服中の患者では頭蓋内出血の可能性を認識する
●初回CTで頭蓋内出血が認められる場合は、予め時間を決めて再度、頭部CTを撮影することも考慮する
- 抗凝固薬・抗血小板薬内服中や初回CTで頭蓋内出血の所見がある患者では、急激に頭蓋内病変が進行する可能性がある。
【ポイント】
凝固・線溶系の障害、血小板減少症の病態では、神経学的所見が出現してから頭部CT撮影を行った場合、手術などの治療が間に合わない可能性もある。
提言3:
●出血などの異常所見があれば、脳神経外科医師の管理下に手術ができる体制で診療を行う
●脳神経外科医師がいない場合は、手術が可能な病院へ転送できる体制を構築しておく
- 急性硬膜下血腫でも脳表の静脈から出血する脳挫傷の少ないタイプでは迅速な血腫除去により救命される可能性もある。
- 手術が必要な頭部外傷発生時の転送を含めた診療方針や判断について院内で検討し明文化しておく。
【ポイント】
転倒・転落による頭部外傷の事象発生に備え、転倒・転落後の診断と対応について検討しておくことが推奨される。
■頭部への衝撃を和らげるための方法
提言4:
●ベッド柵を乗り越える危険性がある患者では、ベッドからの転落による頭部外傷を予防するため、衝撃吸収マット、低床ベッドの活用を検討する
●転倒・転落リスクの高い患者に対しては、患者・家族同意のうえ、保護帽の使用を検討する
- 保護帽および衝撃吸収マットには転倒・転落時に身体に加わる急激な力を緩和する効果は期待できる。
【ポイント】
ベッド柵を乗り越える能力のある患者へは、離床の誘因を取り除き、適切なタイミングで患者の行動をサポートする配慮も重要となる。
■転倒・転落リスク
提言5:
●転倒・転落歴は転倒・転落リスクの中でも重要なリスク要因と認識する
●認知機能低下・せん妄、向精神薬の内服、頻尿・夜間排泄行動も転倒・転落リスクとなる
●転倒・転落歴
転倒・転落につながるヒヤリ・ハットや同じ状況で転倒・転落を繰り返す可能性が高い。
●認知機能低下・せん妄など
ナースコールを押して介助の必要性を知らせることが難しく、一人で歩行してしまう。
●向精神薬
睡眠薬や抗精神病薬の副作用によりリスクが高くなる。
●頻尿・夜間排泄行動
加齢性変化による尿便意の切迫状態が気持ちの焦りとなり、健康時のボディイメージのまま行動する。
提言6:
●転倒・転落リスクの高い患者への、ベンゾジアゼピン(BZ)系薬剤をはじめとする向精神薬の使用は慎重に行う
- 高齢者では薬剤の感受性が高まり、代謝や排泄が遅延するため、健忘や認知機能障害、せん妄などの副作用が現れやすい。
- 向精神薬との多剤併用は転倒・転落リスクがより高くなる。
【ポイント】
せん妄に対しては、薬物対応の前に、まず、原因の除去や早期離床、環境整備といった非薬物的対応に努めることが望まれる。
■情報共有
提言7:
●入院や転倒による環境の変化、治療による患者の状態変化時は、転倒・転落が発生する危険が高まることもあるため、患者の情報を共有する
- 多職種が多く勤務する日勤帯に、夜間と日中の状況をふまえて転倒・転落リスクを分析して予防対策を検討し、夜勤帯へ伝達する。
- 転倒などの環境の変化や患者の状態変化によって、転倒・転落リスクが高まることを認識し、転倒・転落リスクを再評価する。
【ポイント】
高齢者や認知機能低下の患者では、環境の変化などで混乱をきたす可能性があるため、転倒前の転倒・転落リスクに関する情報や入院前の患者情報が重要となる。
■転倒・転落予防に向けた多職種の取り組み
提言8:
●転倒・転落リスクが高い患者に対するアセスメントや予防対策は、多職種で連携して立案・実施できる体制を整備する
- 多職種の医療スタッフがそれぞれの専門性を活かして患者のリスクを分析・評価し、個別のケアプランを多職種で構成されるチームで検討する。
- ヒヤリ・ハットを含む転倒・転落に関する事象についての検討会や院内研修を開催する。
【ポイント】
個別の状況に合わせた転倒・転落予防対策の立案・実践・評価が重要である。
詳しくは、下記の日本医療安全調査機構Webサイト参照
https://www.medsafe.or.jp/modules/advocacy/index.php?content_id=1
×close