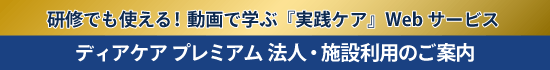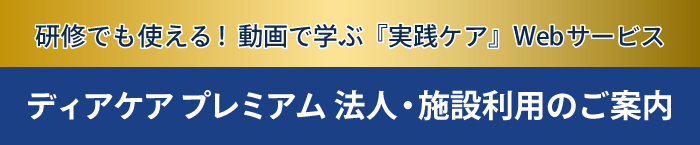ニュース
2020/1/8
世界で初めて認知症カフェの実態を大規模調査
社会の高齢化に伴って日本国内での認知症患者は増えており、2025年には約700万人(高齢者の5人に1人)になると推測されている。わが国では、2012年の「オレンジプラン」によって本格的な認知症施策が始まり、その一環として地域に認知症カフェを設置することが推奨された。認知症カフェは、認知症の人とその家族を支援することを目的にしており、気軽に立ち寄れて地域の人たちのつながりを作るきっかけになる新しい場所である。2015年1月に改訂となった「新オレンジプラン」においても認知症カフェの活動が推進され、2018年度末には全国に7,000カ所の認知症カフェがある。
認知症カフェは、これまでどのように実施され、どのような人に効果があるのかは十分に把握されていなかった。日本でも、認知症の人と家族、地域住民、専門職等の誰もが参加できて集う場所と定義されるが、具体的な運営方法や効果については実施者の裁量にゆだねられてきた。
そこで藤田医科大学などの研究グループは、2016年度厚生労働省老人保健健康増進等事業(老健事業)によって行われた「認知症カフェの実態に関する調査研究事業」をもとに、世界で初めて認知症カフェに関する大規模なデータ解析を行った(国内1,477カ所のうち有効回答であった1,335カ所を分析)。
開催頻度については、1ヵ月に1回のカフェが64.8%と最も多く、1回あたりの開催時間は2時間が53.8%と最も多いことがわかった。運営者、認知症の人の家族、地域住民それぞれの評価は下記の通りである。いずれの場合も、同じ立場の人が多く参加していることが効果に関係していることが示された。
- 運営者による評価では、認知症の人にとっては開催頻度がより頻繁で、コンサートなどの催しがあることが効果的であるとした
- 認知症の人の家族による評価では、開催頻度は関係がなく、カフェで専門職と相談ができること、同じ立場の人同士で話し合いができることが効果的であるとした
- 地域住民による評価では、開催頻度が多く、認知症に関する講話があることや専門職に相談できることが効果と関係しているとした
今回の研究結果によって、以下のようなことが示された。
- 1カフェによって割合は異なるものの、3者が参加して1ヵ月に1回、2時間という形で実施されることが主流であること
- 2認知症カフェの源流とされるオランダのアルツハイマーカフェでは、30分ごとなどに区切ってミニ講話や話し合い、コンサートなどの行事が2時間の間に行われてきたが、そのように運営することでいずれの立場の人の望みも叶えていると推測されること
ただし、運営者の考え方やそれぞれの地域や参加者のニーズに合わせて、カフェの開催や内容にはバリエーションが生じる可能性もあるとしている。
今後、認知症カフェは高齢化が進む世界各国で増えていくと予想されており、同研究グループは、今回の研究成果が多くの地域での実践につながることが期待されるとしている。
詳しくは、下記の藤田医科大学Webサイト参照
×close