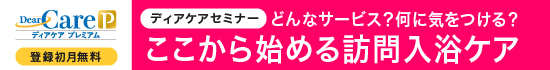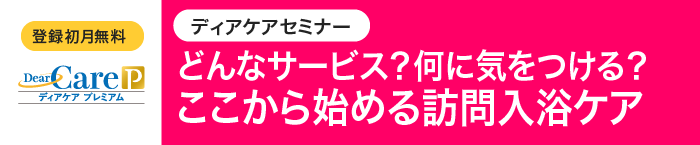ニュース
2020/5/20
看護師の正規雇用職員の離職率、給与はともに横ばい傾向 -「2019年病院看護実態調査」結果報告
公益社団法人日本看護協会では、病院看護職員の需給動向や労働状況、看護業務の実態等の把握を目的に「病院看護実態調査」を毎年実施している。最新版の2019年の調査では、例年どおり離職率や給与、夜勤状況の調査に加え、新たに多様な勤務形態の導入、地域における病院の役割認識および実施状況についてもとりまとめられた。
病院看護職員の離職率は例年通りの結果へ
正規雇用看護職員、新卒採用者、既卒採用者の離職率について、2019年の調査結果では過去6年間の調査結果とほぼ変わらない数値であり、横ばい傾向が続いている。離職率はそれぞれ正規雇用看護職員が10.7%、新卒採用者が7.8%、既卒採用者が17.7%であった。
近年、既卒採用者の離職率がやや高い割合で推移しており、既卒採用者の約6人に1人が、再就職後、採用された年度内に退職していることがわかる。このことから、同協会では、既卒採用者の定着促進に向けた実態や課題の把握などが今後の課題としている。
給与・夜勤手当もほぼ横ばい傾向
「新卒看護師の予定初任給」(諸手当を含む平均税込給与総額)は、「高卒+3年課程」で264,307円、「大卒」で272,018円であった。例年を通して大きな変動はなく、ほぼ横ばい状態である。なお、2019年より初めて大学院卒の給与が調査されており、その「平均税込給与総額」は277,472円だった。
「勤続10年、31~32歳、非管理職者」の看護師の月額給与は320,773円であり、こちらも横ばい状態が続いている。
夜勤手当の平均額は、「三交代制準夜勤」で4,141円、「三交代制深夜勤」で5,033円、「二交代制夜勤」で11,026円であった。2010年の調査以降、全体としてほぼ横ばいの状況が続いている。
整いつつある個々の状況に応じた働き方
夜勤状況の調査では、夜勤を行っている部署に所属し、「2019年9月の1か月間に夜勤を行わなかった正規雇用看護職員の割合」は13.5%であった。2018年の19.1%と比較すると減少している(*1)。
日本看護協会では、13.5%という結果に対し、「約7人に1人が夜勤を行う部署において夜勤を実施しなかったということであり、育児・介護などの個々の状況に応じて働き続けられる環境が整いつつある」と分析している。しかし、その一方で「夜勤者の確保の困難さ」があることも指摘する。
また、ワークライフバランスの充実が求められる昨今の状況をふまえ、法定外で実施されている制度についても調査された。法定外制度のうち「院内規定に明記」されたものの中で最も多かったのは「年休が半日単位で利用できる制度」で、全体の72.0%の実施割合であった。「規定ではないが運用で対処」を含めると全体の91.3%にも及ぶ。
この「規定ではないが運用で対処」されている制度のうち最も多かったのは、「育児・介護の理由以外の夜勤への配慮(夜勤の免除や回数軽減」(70.1%)であり、先ほどの夜勤状況の調査結果ともつながる結果が得られている。こうした制度が柔軟に取り入れられ、職場の環境整備が進むことで、看護職員一人一人の生活と仕事に好循環が生み出されることを期待したい。
地域における病院の役割認識および実施状況には若干のギャップあり
地域における病院の役割認識と実施状況についても調査された。
全体の約7割の病院において「担う必要がある」と認識されている役割は、「退院前の患者宅への訪問指導の実施」(69.8%)であった。次いで「地域住民への教育・啓発活動」(68.3%)であり、「退院後の患者宅への訪問指導の実施」(63.8%)と続く。
それに対して、実際に行っている活動(「積極的に行っている」と「必要に応じて行っている」の合計)では、「地域住民への教育・啓発活動」(63.7%)が最も高い割合だった。役割認識で高い割合を示した「退院前の患者宅への訪問指導の実施」は59.8%であり、役割認識とは若干のギャップが生じる実態となった。
詳しくは、下記の日本看護協会Webサイト参照
「2019年病院看護実態調査」結果
https://www.nurse.or.jp/up_pdf/20200330151534_f.pdf
引用文献
*1. 日本看護協会: 2018年 病院看護実態調査
https://www.nurse.or.jp/nursing/statistics_publication/publication/research/index.html
×close