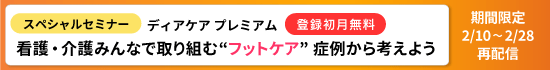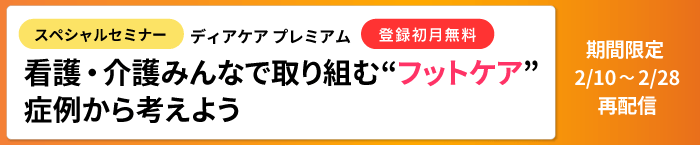ニュース
2021/2/22
持参薬の処方漏れを多職種連携で防ぐ
高齢化に伴い、基礎疾患を重複して抱え、複数の処方薬を服用している患者は多くみられる。入院等で環境が変わる際は、医療者は患者に処方されている薬剤を漏れなく確認して院内処方に切り替えるなど、確実な継続が必要である。
一方で、患者の持参忘れや、入院時の確認不足などによって、本来服用すべき薬剤の継続が止まってしまう事例もみられる。公益財団法人日本医療機能評価機構が発信する「医療事故情報収集等事業 医療安全情報」によると、入院時、持参薬鑑別書の情報や確認が不足したことにより、持参薬の処方内容を継続するための処方・指示が漏れた事例が9件報告されている(集計期間:2017年1月1日~2020年10月31日)。
本報告では、特に以下の2件を事例として取り上げており、持参薬の継続漏れによって実際に患者の病態にも影響が出た例があることがわかる。
【事例1】
患者は心房細動のためリクシアナ錠を服用していた。入院時、薬剤師は患者が持参した薬剤を持参薬鑑別書に登録したが、患者が持参していなかったリクシアナ錠に気づかなかった。医師は、持参薬鑑別書を確認して処方した。7日後、下肢に動脈血栓症を認め、リクシアナ錠の処方が漏れていたことが判明した。
【事例2】
患者は慢性心不全のためフロセミド錠を服用していた。入院時、医師は持参薬鑑別書による報告を待たずに薬剤を処方し、その際、フロセミド錠の処方が漏れた。その後、薬剤部での持参薬の鑑別が終了し、持参薬鑑別書が作成された。処方された薬剤が病棟に届いた際、漏れがないか誰も確認しなかった。フロセミド錠を服用しなかったことで患者の心不全が悪化した。
これらの事例が発生した医療機関の取り組みとして、下記が挙げられている。
・患者が持参した薬剤だけでなく、薬歴が分かる複数の情報で現在服用中の薬剤を確認する。
・医師は、持参薬鑑別書を確認して処方や指示をする。
・多職種で持参薬の継続や中止の確認ができる仕組みを構築する。
*上記は一例であり、自施設に合った取り組みを検討すること
慢性疾患の治療のために処方されている薬のなかには、服用をやめてもただちに影響がみられないものもあり、患者自身も飲み忘れや処方漏れに気づかないこともある。患者・家族と接する機会が最も多い看護師は、会話等のなかから薬剤の服用に関連した話題を引き出し、拾い上げることで、処方漏れを防ぐための一助となることが期待される。処方に直接かかわる医師や、薬剤の専門家である薬剤師と連携し、多職種で処方薬の継続を維持することが求められている。
詳しくは、下記の日本医療機能評価機構Webサイト参照
「持参薬の処方内容を継続する際の処方・指示漏れ」
×close