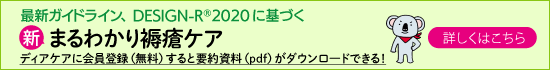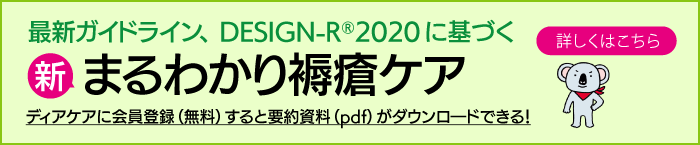ニュース
2025/4/22
「高齢者救急問題の現状とその対応策についての提言2024」が出される 日ごろから“いざというとき”の対応を本人・家族・職員と話し合うことが大切
超高齢社会が進行するわが国において、高齢者の救急搬送件数と救急搬送時間は増え続けている。人生の最終段階での体に負担のかかる治療を希望せずに、生活の場である高齢者施設や在宅での看取りを希望する方、DNAR(do not attempt resuscitation)を表明する方もいるなかで、そのような方が急変や心停止となった際に救急車が呼ばれ、意に沿わない医療行為が行われたり、遠方の病院へと搬送される例も少なくない。
このような高齢者救急への課題に対して、日本救急医学会をはじめとする14の団体が共同して「高齢者救急問題の現状とその対応策についての提言2024」を策定・公開した。
本提言は大きく2つのパートに分けられており、前半は対象(市民、高齢者施設の管理者や職員、急性期~慢性期病院など)ごとへの提言、後半は、高齢者救急の現状とその対応策についてまとめられている。
本提言のなかでキーワードの1つと言えるのが、「ACP(アドバンス・ケア・プランニング)」ではないだろうか。人生の最終段階をどのように過ごしたいか、どのような医療を行ってほしい(行ってほしくない)か、意思が伝えられなくなったときに誰に代弁してもらうのかなど、日ごろから繰り返し話し合い、本人・家族、医療・福祉スタッフで共有しておくことで、望まない救急搬送を避けることにもつながる。
また、DNARを表明していても、実際の急変に直面した際に慌てて救急車を呼んでしまうケースも少なくない。医療者は家族に対して、今後起こりうる状態変化の可能性などをていねいに説明し、自身でも想定しておくとともに、在宅や施設で急変が起こったときの対応や報告体制を、施設として整備しておくことも重要だ。
なお、本提言はあくまで、高齢者が救急医療を必要としたときに、適切で意に沿った医療を受けることができ、その後も納得できる暮らし方を選ぶことができるようにするためのものであり、決して高齢者への救急医療を差し控えるためのものではないことも明記されている。
高齢化は今後も続くとみられ、生活の場で看護師や介護士が臨終期の患者のケアにかかわる機会も増えてくるだろう。“いざというとき”に、本人や家族の望む最期を迎えられるよう、本提言の内容を理解し、スタッフ間でも共有しておきたい。
詳しくは、下記、日本救急医学会Webサイトを参照
「高齢者救急問題の現状とその対応策についての提言2024」
https://www.jaam.jp/info/2024/info-20241220.html
【関連ページ】
●在宅で遭遇する急変(急な状態変化)への対応
https://www.almediaweb.jp/critical-care/critical-care-001/
●「ディアケア プレミアム」
在宅の場で取り組みたいアドバンス・ケア・プランニング(ACP)
~訪問看護師が支える意思決定支援~(セミナー)
https://dearcare.almediaweb.jp/home/cat19/theme002/index.html
●臨終期(看取り期)の症状と経過に合わせたケア
https://www.almediaweb.jp/expert/feature/2503/
●「最期まで自分らしく」をかなえる看取りケア
https://www.almediaweb.jp/endoflife-care/endoflife-care-001/
●看護師と地域連携で支える在宅ターミナルケア(終末期医療)の実際
×close