2022年11月公開
BPSDの捉え方は、表1に示すようにさまざまです。
表1 BPSDの捉え方
横にスクロールしてご覧いただけます。
| 種類 | 捉え方 | 見抜きたいポイント |
|---|---|---|
| 医学モデルとしてのBPSD | 健常者ではみられない異常な行動と捉える | 体調や薬剤との関連も含め、異常行動を見抜く |
| 適応・順応行動としてのBPSD | まわりの環境に適応しようとして生じている行動と捉える | 本人が環境に適応できているかどうかを見抜く |
| 自己表現行動としてのBPSD | 自己を表現しようと努力している行動と捉える | 本人が何を訴えようとしているのかを見抜く |
| 内面表出サインとしてのBPSD | “心の叫び”として表れている行動と捉える | 本人が内面で何を抱えているのかを見抜く |
| アンメットウォンツサイン(unmet wants sign)、 アンメットニーズサイン(unmet needs sign)としてのBPSD |
目に見えない要望が満たされていないことから生じている行動と捉える | BPSDに隠されているニーズ・要望を見抜く |
文献1,2を参考に作成
ぜひ理解していただきたいのは、BPSDは介護する人にとって「困る症状」ではありますが、認知症患者さん本人にとっては、「助けて」のサインであるということです。
私は、BPSDは、「本人や介護者のお困りごと」であると捉えています。脳の病変(疾患)や認知症状(中核症状)だけでなく、薬剤、せん妄、体調、各疾患、環境、ケアや対応、生活状況、性格、個人史など、BPSDは多くの要因が影響し合って生じます。だからこそ、原因を見抜くためにその人を包括的に捉える必要があるのです。
〈文献〉
BPSDは、過活動性(陽性)と低活動性(陰性)の2種類に大きく分けられます。認知症の型によっても、表れやすい症状は少しずつ異なります(表2)。
表2 認知症の型別に表れやすい症状
横にスクロールしてご覧いただけます。
| 認知症の型 | 主な認知・神経症状 | 過活動性BPSD | 低活動性BPSD |
|---|---|---|---|
| アルツハイマー型 | 記憶障害、見当識障害、空間認知障害 | 易怒性、無断外出、繰り返し質問 | 不安、アパシー |
| レビー小体型 | 幻視、覚醒レベルの変動、パーキンソニズム | 妄想にもとづく多動や暴言・暴力 | うつ、不安 |
| 前頭側頭型 | 社会脳障害(ルール無視、共感しない)、脱抑制、常同行動 | 易怒性、暴言、暴力、時刻表的生活、一気食い | アパシー(重度期) |
文献3、p8 表1 より一部抜粋
過活動性BPSDは、易怒性、無断外出、繰り返しの質問などがあり、ケアを進めるうえで支障を来たしたり、患者さんの安全に支障を来たしたりする恐れもある、目立つ行動です。
一方、低活動性BPSDはうつやアパシー(無気力、無関心)等があります。あまり目立つこともなく、見過ごしやすい症状です。低活動性BPSDの患者さんは、介護者にとっては手がかからないと思われがちですが、廃用が進むことが問題になります。
ここで、代表的なBPSDをいくつか紹介し、その原因について紹介します。原因を考えることは有効なケアにつながるため大変重要です。
「あなた、私の財布を盗ったでしょう?」「夫が浮気をしている」「私をのけ者にしようと皆がたくらんでいる」などの言動を聞くことがあります。これは、過活動性BPSDのひとつ、妄想であり、他人が訂正できないほど、本人が強く思っています。アルツハイマー型認知症の患者さんによくみられる、もの盗られ妄想や被害妄想、レビー小体型認知症の幻覚・幻視に伴い生じる妄想などがあります。
妄想が生じる原因としては、認知機能の低下で状況判断が困難であることが挙げられます。また、周囲との関係が希薄であり、患者さんの根底に不安や孤独、寂しさ、疎外感、不信感が潜んでいることが多いです。

家に帰れない状況のなか、何度も「家に帰りたい」と強く訴えることがあります。病院や施設にいる患者さんだけに限らず、家にいても訴えることがあり、放っておくと無断外出や徘徊、行方不明につながる恐れがあります。なお、繰り返し同じことを訴える、というのも、BPSDの症状のひとつです。
このような訴えは、見当識障害によって自分が今どこにいるのかがわからないことが原因である可能性があります。また、「ここは自分の居場所ではない」と感じていたり、居心地の悪さから帰宅願望が生じている可能性があるため、本人が落ち着ける、居心地のいい環境づくりが求められます。
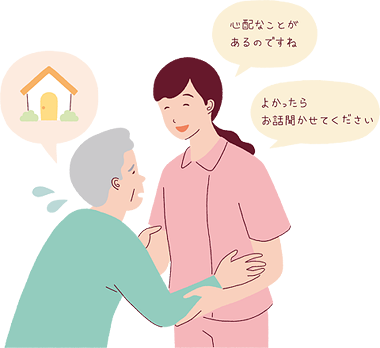
物を投げる、大声や暴言を吐く、暴れる、叩く、かみつく、引っかくなどの行動は、代表的な過活動性BPSDです。ときには、必要な点滴を抜いてしまったり、立ち歩いてしまうことで安静が保てなかったりと、患者さん本人にも危険が伴い、介護者も困ってしまう状態です。
このように患者さんの反応が爆発してしまう原因には、さまざまなものが考えられます。本人の気分や体調が悪いこと――例えば、痛みやかゆみ、空腹、便秘、トイレに行きたい、頻尿、尿閉、不眠、発熱などが不快感を高めます。入院による環境の変化も原因として考えられます。周囲の騒音や機器の音、人の声、暑い・寒いことや明る過ぎる照明などが、不快感を高める要因となります。
これらに加えて、気に障ることを周囲の人から言われると、本人の怒りのスイッチが入ることになります。
体調をみること、環境に配慮すること、そして私たちの対応にも注意することが求められます。
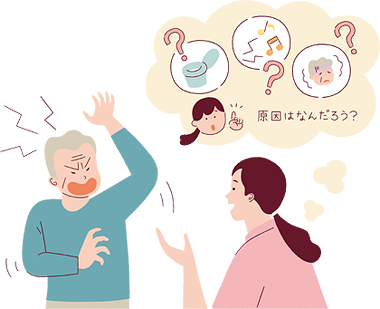
「誰にも必要とされていない」「何もいいことがない」「何がなんだかわからない」などと悲観的になってしまう方がいます。低活動性BPSDのひとつ、うつ症状です。大きなストレスや出来事が引き金となり、悲観的な態度や言動、だるさや意欲の低下が長い間続きます。
原因としては、認知症の進行に伴ってできなくなっていくことが増えること、それによって周囲から厳しく非難されたり、自信をなくしたり、疎外感を感じることが挙げられます。
また、うつと似た状態として鑑別が必要なのが、アパシー(無関心)です。やる気がなく、意欲低下や感情の乏しさがあるものの、悲観的な感情がないのがうつとの違いです。本人は困っておらず、介助者も特に困ることはありませんが、放っておくと1日中活動もせずテレビなどを見ていたりして廃用が進んでしまうため、注意が必要です。

〈文献〉
会員登録をすれば、
Part3、Part4も読めます!
認知症患者への具体的看護ケアの実際
限定コンテンツ
実践のコツや記事などの
「限定コンテンツ」が見られる!
資料ダウンロード(PDF)
一部の記事で勉強会や
説明など便利に使える資料を公開中!
ケア情報メール
新たなコンテンツの
公開情報や、ケアに役立つ情報をお届け!
実践ケア動画
エキスパートのワザやコツが
学べる動画を多数掲載!
期間限定セミナー動画
各分野のエキスパートが登壇。
1回約15分で学べる!
電子書籍
書店で販売されている本や、
オリジナル書籍が読み放題!