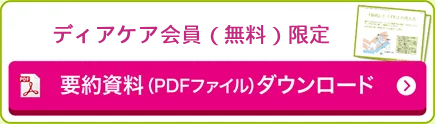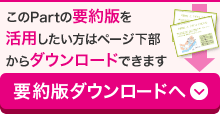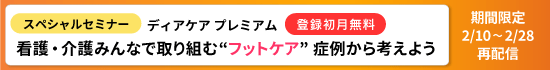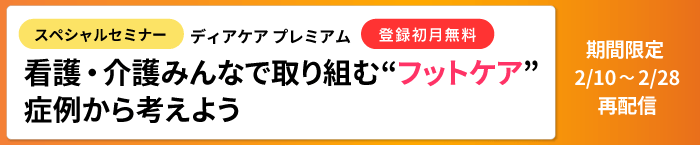Part11 在宅の褥瘡(じょくそう)患者にどうアプローチする?在宅で利用できる福祉用具と衛生材料を知っておこう
2023年2月更新(2016年6月公開)
1.福祉用具の活用
介護保険で福祉用具を利用するためには、要支援・要介護認定を受けておく必要があります。介護保険サービスは、介護認定を受けて、ケアマネジャー等が策定するケアプランによって利用可能になります。
介護保険による福祉用具には2通りあります。貸与(レンタル)できるものと、購入費が支給されるものです(表1)。
貸与されるものは、車椅子、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープなど13 種目あります。これらは原則として、利用者の身体状況や要介護度の変化、福祉用具の機能の向上に応じて適時・適切に提供できるものです。
一方、販売される種目は、使用により形態や品質に変化の出るものや再利用できないものなど、貸与になじまないものです。腰掛便座や簡易浴槽、入浴補助具などが該当します。購入費は原則年間10万円を限度としています。介護保険を利用することによって1割負担になります。
これらの福祉用具は、ケアマネジャーか福祉用具専門相談員らと相談のうえ選定し、貸与・購入する際は、自治体が指定する専門事業者を通じて行います。
表1 介護保険による福祉用具(対象項目)
| 福祉用具貸与(原則) | ・車椅子 ・車椅子付属品 ・特殊寝台 ・特殊寝台付属品 ・床ずれ防止用具 ・体位変換器 ・手すり ・スロープ ・歩行器 ・歩行補助つえ ・認知症老人徘徊感知機器 ・移動用リフト(吊具の部分を除く) ・自動排泄処理装置 |
|---|---|
| 福祉用具販売(例外) | ・腰掛便座 ・自動排泄処理装置の交換可能部 ・入浴補助用具(入浴用椅子、浴槽用手すり、浴槽内椅子、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト) ・簡易浴槽 ・移動用リフトの吊り具の部分 |
【給付制度の概要】
- ①貸与の原則
利用者の身体状況や要介護度の変化、福祉用具の機能の向上に応じて、適時・適切な福祉用具を利用者に提供できるよう、貸与を原則としている。 - ②販売種目(原則年間10万円を限度)
貸与になじまない性質のもの(他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うもの、使用によってもとの形態・品質が変化し、再利用できないもの)は、福祉用具の購入費を保険給付の対象としている。 - ③現に要した費用
福祉用具の貸与及び購入は、市場の価格競争を通じて適切な価格による給付が行われるよう、保険給付における公定価格を定めず、現に要した費用の額により保険給付する仕組みとしている。
厚生労働省:介護における福祉用具貸与.を元に作成
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000314951.pdf(2022/8/5アクセス)
2.衛生材料の活用
褥瘡ケアにおいてはさまざまな衛生材料が必要になります(表2)。衛生材料には、「在宅療養指導管理料を算定している場合に医療機関が提供できるもの」としてガーゼ、ドレッシング材、サージカルテープ、消毒薬などがあります。これらは医療機関が在宅療養者に必要で十分な量を供給します。また、処置用シーツや滅菌手袋などは在宅療養者が購入するものになります。看護師や在宅主治医は訪問する際に、使用する滅菌手袋やメジャーを持っていきます。
また、訪問看護事業所で購入・保管できる衛生材料もあります(表3)。これは「薬事法の一部を改正する法律の施行等について」(2009年)によって、訪問看護ステーションで緊急時に必要となる衛生材料を購入できるようになったためです。訪問看護で使用した衛生材料は医療機関に請求します。さらに現在は、在宅療養管理指導を行っている保険医療機関の医師の処方箋に基づき、保険薬局で皮膚欠損用創傷被覆材と非固着性シリコンガーゼを支給できるようになっています。
在宅においては、さまざまな衛生材料、医薬品を療養者宅で管理する必要があるため、種類や量、使用期限などをこまめにチェックして管理し、必要なときに不足しないような適切な管理が重要です。そのため、療養者・家族を中心にして、かかわる職種が情報を共有していくことが大切です。
表2 在宅での衛生材料の種類
| 在宅療養指導管理料を算定している場合に医療機関が在宅療養者に提供する物品 | ・ガーゼやドレッシング材 ・サージカルテープ ・消毒薬 ・洗浄のための物品 |
|---|---|
| 在宅療養者が購入する物品 | ・処置用シーツ ・滅菌手袋 ・石けん ・スキンケアに必要な物品 ・洗浄用のボトル |
| 看護師、在宅主治医が持参するもの | ・滅菌手袋 ・メジャー |
表3 訪問看護事業所で購入・保管できる衛生材料(例)
- ガーゼ
- 脱脂綿
- 綿棒
- 綿球
- 滅菌手袋
- 絆創膏
- 油紙
- リント布
- 包帯
- テープ類
- 医療用粘着包帯
- ドレッシング材
- 使い捨て手袋
日本看護協会:衛生材料等の整理.を元に作成
http://jvnf.or.jp/newinfo/20111019-2.pdf(2022/8/5アクセス)